「とりあえず見て学べ!」
「忙しいから後で教える!」
「やってみて覚えて!」
工場という閉鎖された空間では、先輩社員からやり方を教わり、知識を身に着けていくことが多いです。それゆえに“古いやり方”が根付いていることも多いです。
そして、そのやり方は必ずしも「正しいやり方」とは限りません。
私は10年以上工場で働いた経験を通じて「自己学習」の大切を学びました。
自己学習では「読書」がオススメです。
工場勤務が読書?と疑問に思われるかもしれませんが、自己学習で最も簡単なのが「本を読むこと」だと考えています。
- 正しい知識が得られる
- 自分の好きなタイミングで知りたいことが知れる
- 低価格で学べる
このように「本を読むこと」は様々なメリットがあります。

私は本から知識を得て、実践していくこと10年以上。
現在はプライム上場企業の工場でラインリーダーをしています。
もちろん諸先輩方の指導あってのことだと思いますが、本を読むことで差をつけられた実感もあります。
- 工場勤務で伸び悩んでいる人
- 工場配属になった人
本記事では、そのような方に向けて「私が読んだ工場勤務にオススメの本」をご紹介していきます。
なぜ工場勤務が本を読むのか
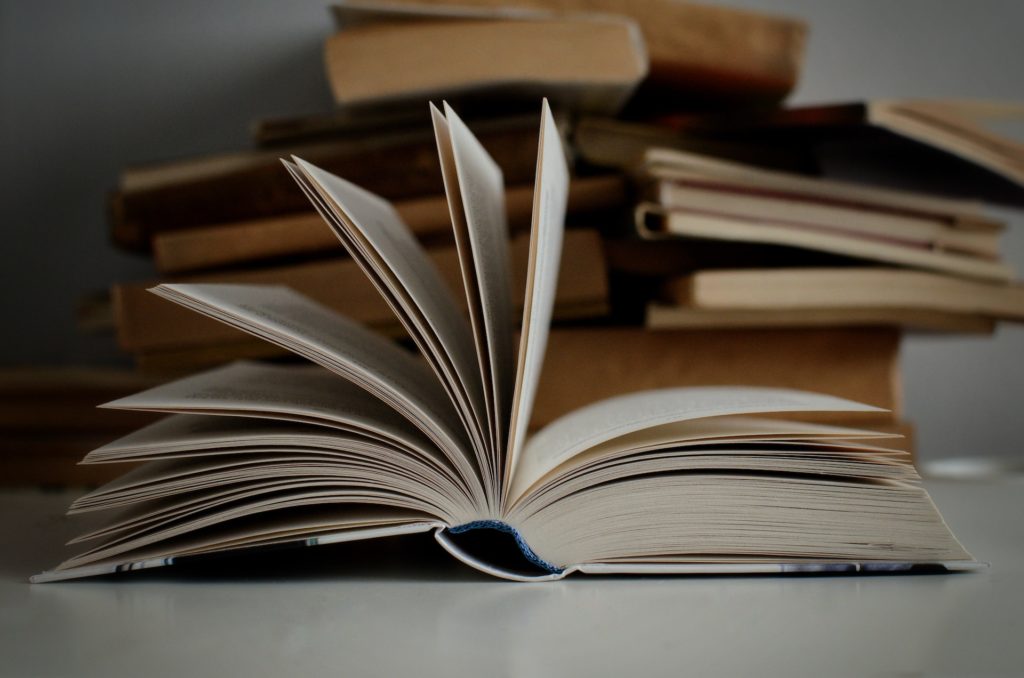
工場での教育は、OJTと通信教育が一般的ではないでしょうか。
On the Job Training (オンザジョブトレーニング)の略で、職場の上司や先輩が、部下や後輩に対して、実際の仕事を通じて指導する教育方法
私は10年間工場で働いてきましたが、基本的にOJTで学んできました。
それにプラスして、会社で通信教育を受講できる仕組みもあったので、できる限り受講し今まで20件近く受講しました。
しかし、教育を受ける中でそれらには問題点があると考えています。
- OJTで自己流が広がってしまう
- 忙しいを理由にOJTが中途半端
- 通信教育はコスパが悪い
- 通信教育はミスマッチが発生しやすい
一つずつ説明していきましょう。
OJTで自己流が広がってしまう
手とり足取り先輩が教えてくれた知識は「正しい知識」でしょうか?
私の経験談を少し書きます。
ある部品が破損して、ラインが半日近く停止してしまったことがありました。
原因は「交換方法が違ったこと」
当事者に話を聞いたところ、交換方法は先輩社員に教わったとのこと。その先輩社員さらに上の先輩社員に…
このように数十年にわたり、間違った知識がその現場の「正しい知識」として存在していることは珍しくありません。
その知識の発信源が曖昧だとこのようなことが発生してしまいます。
忙しいを理由にOJTが中途半端
OJTの場合、教える側の力量や職場の環境で取得できる知識に差が生じます。
右も左もわからない新入社員時代、私は先輩に1日中付いて回り仕事を学んでいました。
しかし、人員不足でバタバタした職場だったので、
「忙しいから後で教えるね!」
「バタバタしてるからとりあえず見といて!」
これが現場でいわれる「見て盗め」の所以かもしれません。
そんな感じで1年が経ち、たいして教えてもらえないまま独り立ち。そして、そこから失敗の連続。
精神的にかなり辛かったですが、そこから私は「自己学習」の大切さを学べました。
通信教育はコスパが悪い
はじめに断っておくと、全ての通信教育が悪いというわけではありません。
中には技術講座専門のJTEX企業によっては補助が出ることもあると思いますが、たいていは期限や成績など補助に条件があります。
- テストがあり、忙しい現場では時間の融通が利かない
- 1講座数万円するものが多く、コストパフォマンスがいいとは言えない
ただし、
- 資格系の講座
- ある程度の強制力がほしい人
など、条件によっては受講する価値は十分にあります。
通信教育はミスマッチが多い
教材で学ぶとなると、教材が自分に合うかというのはとても重要だと思います。
サンプルで中身が見れたとしても、実際受講してみたら「イメージと違った」なんてことも多々あります。
- 頭に入ってこない
- 高額だから無理やりやる
- 期限があってストレス
よかれと思って始めたのに、教材や内容が合わないために負担となってしまいます。
また、会社側が用意してくれる通信教育は人事部が選定していることが多いと思います。
そもそも取りたい講座がないという経験もあります。
工場勤務が本を読むメリット

以上を理由に私が考える工場勤務が本を読むメリットは3点あります。
- 正しい知識が得られる
- 自分の好きなタイミングで知りたいことが知れる
- 低価格で学べる
まず書籍は出版社から出ている時点で「内容の正確さ」が認められています。
正しい知識を得ることで、自分が教育者になったときのOJTが飛躍的に向上します。そうすれば職場全体のレベルアップにも繋がります。
また、通信教育を実施した際のデメリット
- ミスマッチ
- コスト
- タイミング
をすべて解決できると考えられます。
・書店にいけば中身を確認できる
・数千円で購入することができる
・期限もないので、自分のペースで学習することができる
必要なのは読み続ける「根気」くらいです。
工場勤務にオススメの本
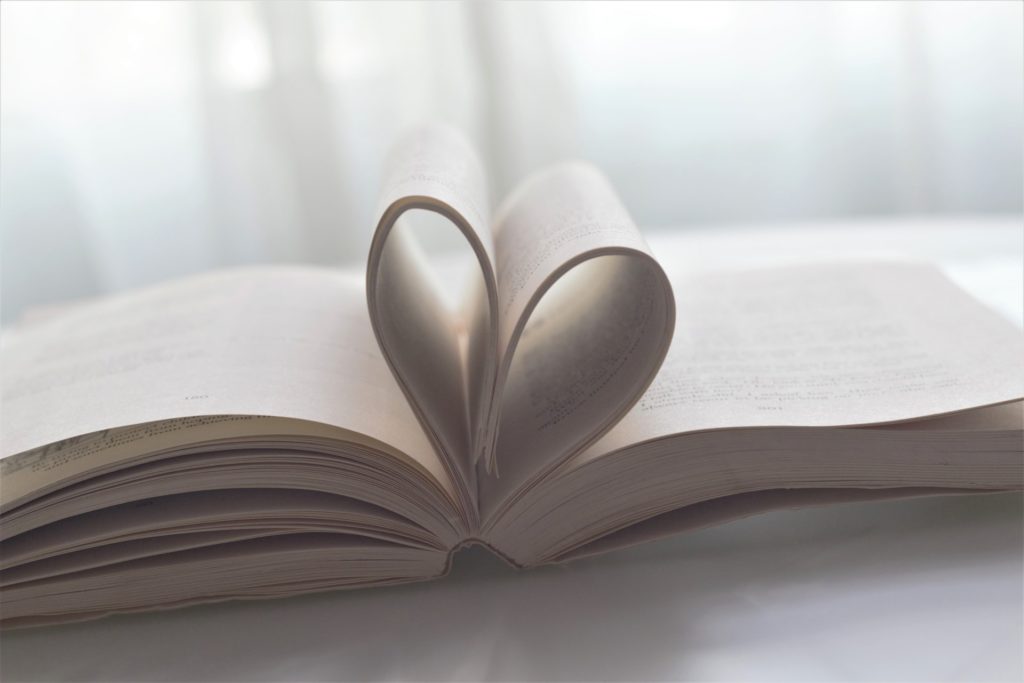
では、ここから具体的なオススメ本を紹介していきます。
簡単な解説と「こんな人にオススメ」を書いていますので、気になった本は是非手にとっていただきたいです。
新人IErと学ぶ 実践IEの強化書
【著者】日本インダストリアル・エンジニアリング協会
【出版社】日刊工業新聞社
【初版発行日】2021/3/24
【ページ数】208頁
IEとは簡単にいうと「改善すること」です。
現場ではいかに業務改善して、コストダウンや生産性を向上させるかが求められます。
本書では「仕組み」を見直すことでムダを省くことを中心に話が進みます。
中身は対話形式で進んでいくので、普段本を読まない方でも安心して読むことができます。
- 現場で改善を進めたい人
- IEをよく理解していない人
新・まるごと工場コストダウン事典
【著者】五十嵐 瞭
【出版社】日刊工業新聞社
【初版発行日】2008/1/1
【ページ数】204頁
「コストダウンせよ!」と言われても、何をしていいかわからないというのが正直なところ。
本書では、材料費、人件費、不良削減、エネルギー削減などなど。様々な視点からコストダウンについて知ることができます。
アイデアが詰まっている一冊ですので、ネタに困ったら見返してみるといいかもしれません。
- 改善案が浮かばない人
- コストダウンに悩んでいる人
ポカミス「ゼロ」徹底対策ガイド
【著者】中崎 勝
【出版社】日刊工業新聞社
【初版発行日】2018/3/21
【ページ数】184頁
ポカミスってなかなか無くならなくて困っていませんか?
ポカミスが発生するには、それなりの理由があります。本書にはそれが書かれています。
人間の心理状態や現場の改善など、図説込みで書かれているのでとてもわかり易い一冊です。
ただ、AIの文字に釣られて購入すると、期待し過ぎになっちゃうかも。
- ポカミスを無くしたい管理スタッフ
- ポカミスをしたくない現場オペレーター
失敗の科学
【著者】マシュー・サイド
【出版社】ディスカヴァー・トゥエンティワン
【初版発行日】2016/12/23
【ページ数】348頁
現場にミスはつき物です。
しかし、その失敗から学習するのか、失敗を放置するのか、失敗を隠蔽するのか。失敗の次にする行動で組織の成長は雲泥の差になります。
工場の話は少ししかありませんが、事例が多く書かれているためイメージしやすい1冊です。
冒頭の医療現場と航空業界の違いだけでも、かなり衝撃的なので読んでみてください。
- 失敗がこわい人
- 最近失敗してしまった人
ちょこっと改善が企業を変える
【著者】柿内 幸夫
【出版社】経団連出版
【初版発行日】2012/10/20
【ページ数】198頁
改善活動にハードルを感じたことありませんか?
本書では改善のハードルを下げるちょこっと改善「チョコ案」を推奨しています。
どちらかというと工場を管理する側の視点でかかれていますが、「16の改善キーワード」などの章は実務者にも知ってもらいたい内容です。
改善の視野が大きく広がる1冊です。
- 職場の改善を加速させたいリーダー
- どんな改善をすればいいかわからない人
今と未来がわかる工場
【著者】多田夏代
【出版社】ナツメ社
【初版発行日】2022/7/14
【ページ数】240頁
これは工場に関わる全ての人に読んでいただきたい。
誰が読んでもどこかに学びがある「網羅性」と「未来への投資イメージ」が湧く本です。
「製造基盤 BASE6」という工場の基本を6つに分類して、現状を理解して改善していく。
専門書はお堅い見た目の本が多いですが、本書はカラーで、ポップで、図が多く読みやすい本です。
これから工場で働く方には、特にオススメです。
詳しくはコチラの記事でも紹介しています。
- 初めて工場で働く新入社員
- 大まかに復習したいリーダーや管理職
ザ・ゴール
【著者】エリヤフ・ゴールドラット
【出版社】ダイヤモンド社
【初版発行日】2001/5/18
【ページ数】560頁
全世界で1,000万人以上読んだといわれている名著。
経営悪化により自身の工場閉鎖を言い渡された工場長アレックスが、閉鎖までの猶予3ヶ月で様々な問題を解決していくマネジメントの物語。
効率化に対する考えが変わり、本当の業務改善が学べる本です。
少々ボリュームのある本ですので、コミック版で重要な点を学ぶのもオススメです。
- 工場の管理職
- 工場立て直しのストーリーを知りたい方
〈図解〉基本からよくわかる品質管理と品質改善のしくみ
【著者】西村 仁
【出版社】日本実業出版社
【初版発行日】2015/10/16
【ページ数】217頁
これだけは言えます「品質管理業務についたら必ず読んでください」
図解ありで見やすい内容、実用的でシンプルな内容。「とにかく読みやすい」そして、重要な部分はしっかりおさえています。
新人さんはまずこの1冊で問題ないです。
- 初めて品質管理業務をやる方
- 工場配属になった新入社員
トヨタ仕事の基本大全
【著者】㈱OJTソリューションズ
【出版社】KADOKAWA
【初版発行日】2015/2/20
【ページ数】383頁
仕事の問題点を見つけ、改善し、日々成長していく。
工場にいると耳が痛いほど聞く「トヨタの生産方式」ですが、これは製造業に関わらず、ビジネスマンとしての考え方を学ぶことができます。
もちろん5S、改善、問題解決の8ステップなど工場で活用できる内容も盛りだくさんです。
- 向上心が薄れてきた若手
- 工場配属になった新入社員
OODA 危機管理と効率・達成を叶えるマネジメント
【著者】小林 宏之
【出版社】徳間書店
【初版発行日】2020/1/29
【ページ数】240頁
業務改善や効率化に欠かせない「PDCAサイクル」
計画(Plan)、実行(Do)、確認・評価(Check)、改善(Action)の頭文字をとったもの。P-D-C-Aを回すことで、仮説と検証を繰り返して業務改善を進めるマネジメント方法。
しかし、毎日忙しい工場現場で働いていると、「ゆっくりPDCAしている余裕がない」と感じることありませんか?
それはPDCAサイクルが落ち着いた平時に行われるサイクルだからです。
そこで、より高速に回せるPDCAとして登場したのが「OODAループ」。
- 観察 Observe
- 状況判断 Orient
- 意思決定 Decide
- 実行 Act
この頭文字をとったもので、「ウーダ」と読みます。
これはアメリカ空軍の戦闘機パイロットが提唱した戦術が発祥とされており、戦況を瞬時に判断し、次の戦術を実行する。いわば高速の意思決定サイクルです。
効率化が進み、瞬時の判断が必要な工場現場にマッチする業務改善サイクルと考えます。
- 業務改善に携わる人
- 瞬時の判断が必要なリーダー
ものづくりの基本
【監修】日本能率協会コンサルティング
【出版社】日本能率協会マネジメントセンター
【初版発行日】2023/8/10
【ページ数】224頁
ものづくりの現場にいたら知っておきたい
- 現場改善
- 品質管理
- 安全衛生
の基礎が網羅されています。
QCって何?安全な職場をつくるためにはどうしたらいい?など
現場にいたら絶対に必要な知識が書かれています。
「基本」と書いてありますが、リーダー・管理職も知っておきたい内容です。
- これから工場で働く人
- 知識をつけたいリーダーや管理職の人
機械保全のための部品交換・調整作業
【著者】小笠原 邦夫
【出版社】日刊工業新聞社
【初版発行日】2022/5/28
【ページ数】192頁
ベルトやチェーンの交換、軸受・プーリーの交換、シールテープの巻き方など、機械保全の基本中の基本ですが、この部分は特にOJTに偏りがちです。
間違えたやり方で実施すると、機械の消耗を早めてしまうことにもなるので正しい知識を身に着けておきたいです。
本書は写真が多いのが特徴ですが、それがすべてカラーであることがオススメする点です。
カラー写真が整っていながら3,000円しないので、専門書としては低価格です。
- 日々メンテナンス業務を実施する人
- 教育係になった人
生産管理のすべてがわかる本
【著者】石川 和幸
【出版社】日本実業出版社
【初版発行日】2022/7/29
【ページ数】214頁
生産管理で働いている方は読んでおきたい1冊。
基本的な部分もわかりやすく書かれていますが、AI・IoT・DXといった将来取り入れていかなければいけない内容も網羅されているのがポイントです。
実践的で便利なことも書いていますので、より効率をあげたい方にもおすすめです。
- これから生産管理業務をはじめる人
- 効率的な工場運営をしたい人
トヨタ リーダー1年目の教科書
【著者】㈱OJTソリューションズ
【出版社】KADOKAWA
【初版発行日】2022/11/24
【ページ数】256頁
トレーナー全員がトヨタ出身という㈱OJTソリューションズが書いたリーダーの教科書。
トヨタで理想とされている「協働力のあるリーダー」について書かれた本です。
本書では「3つの技法」が紹介されています。
- TCS(Toyota Communication Skill)
- TJI(Toyota Job Instruction)
- TPS(Toyota Production System)
それぞれリーダーとしての必要なノウハウが紹介されており、本書では上記のTCSが多く解説されています。
そのため、信頼関係をつくるマインドや部下が自ら動くようになるテクニックなど人間関係のテクニックが多い印象です。
⇒本要約サービスflierで要約を読む
- 良好な人間関係を築きたい方
- 初めてリーダーになった方
入門 トヨタ生産方式
【著者】石井 正光
【出版社】中経出版
【初版発行日】2004/12/1
【ページ数】222頁
工場勤務従事者であれば絶対に知っておきたい「トヨタ生産方式」
私が読んだトヨタ生産方式の本で、最も網羅的で最も読みやすかったのが本書です。
- ジャストインタイム
- 自働化
- カイゼン
といったトヨタ生産方式の基本を学べ、どう現場に導入するかが学べます。
- 工場に勤務する全ての人
- トヨタ生産方式の復習をしたい人
まとめ
本記事では、工場勤務にオススメの本15選をご紹介しました。
この5冊は特に実践的でオススメですので、迷った方はここから選んでみてもいいかもしれません。
- 正しい知識が得られる
- 自分の好きなタイミングで知りたいことが知れる
- 低価格で学べる
メリットはたくさんありますので、ぜひ自己学習に「本」を活用してみてください。
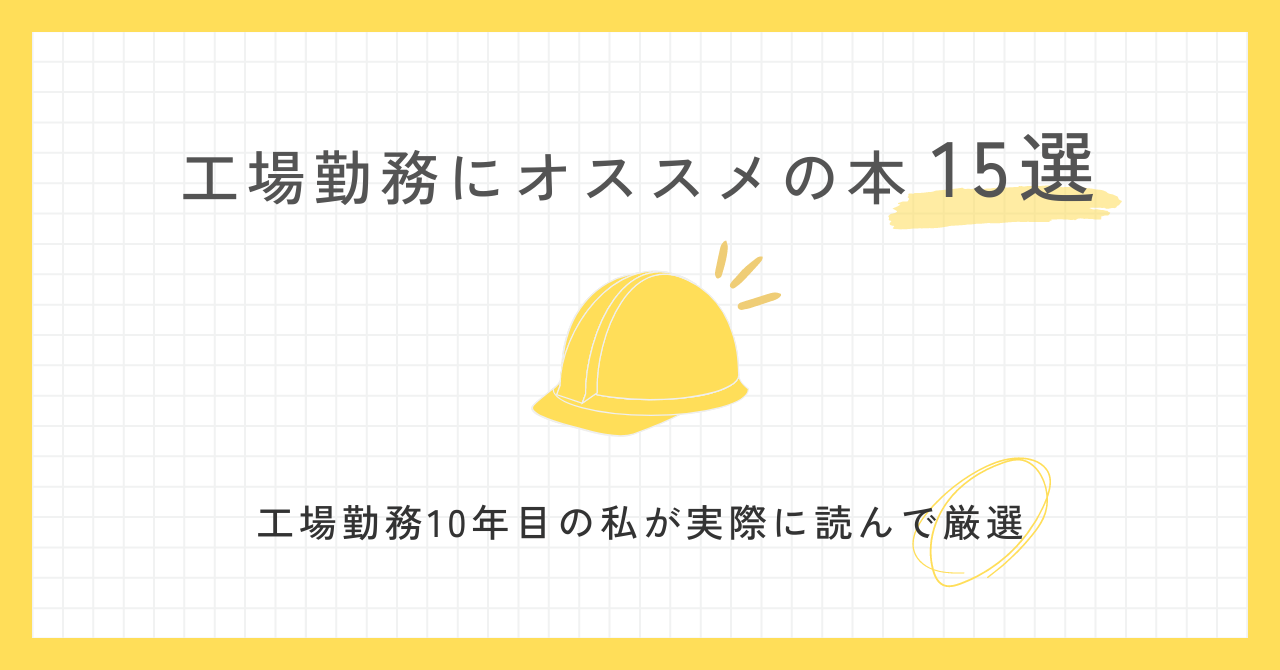

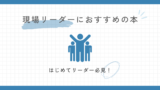


コメント